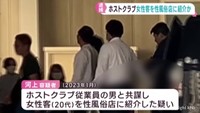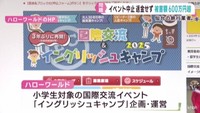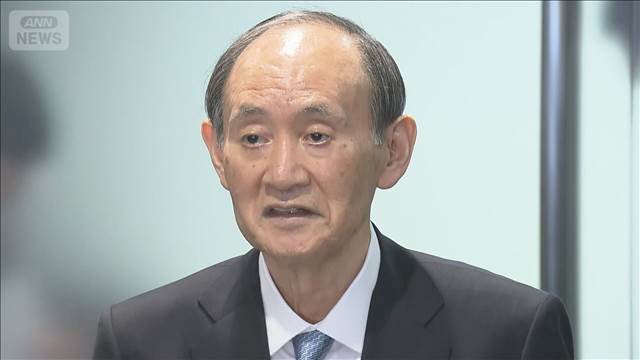伝統的なこけし作りを未来につなごうと、宮城県大崎市でこけしの材料となる木のミズキが工人たちの手によって植樹されました。
大崎市鳴子温泉にある市有林で、こけし工人や市の職員など15人がこけしの材料となる木の1つであるミズキの苗50本を植えていきました。
近年は、ミズキを管理する人員が不足するなど様々な要因でこけしの材料となるミズキが減少しているため、今回植樹したということです。
戦後のこけしブームの際にも材料不足が起こりましたが、当時の工人がミズキを植樹してこけし作りが現在に受け継がれています。 植樹の後は、翌年以降使うためのミズキを採寸し、選定する作業が行われました。
鳴子木地玩具協同組合岡崎靖男代表理事「この木が20年後成長して、将来のこけし屋さんがかわいいこけしを作って皆さんに買っていただければいいなと思います」
参加者「こけし工人を目指すために見習いをしています。まずは鳴子の伝統こけしをしっかりつないでいきたい。若い方も面白いなって思ってもらえるような作品を考えています」
植えられた苗木は20年ほどかけて、こけし作りに適した高さ10メートル以上、幹の太さ20センチ前後に成長するということです。
こけし作りに多く使われるミズキ。名産地の鳴子で作られるこけしの9割以上が、ミズキを材料にしています。
柿澤是伸さんのこけし工房です。1970年(昭和45年)に鳴子温泉上野々に店舗を構え、親子2代でこけし作りを続けてきました。
工房の裏には、こけしに使われるミズキの林があります。秋の彼岸が過ぎて樹木の活動が止まる頃、ミズキは約2メートルの長さに切り出され、1年かけて乾燥させます。
同じくこけしに使われるイタヤカエデは乾燥に2年から3年ほどかかりますが、ミズキは乾燥期間が1年と短いことも特徴です。
その後、こけしのサイズに合わせて丸太を割り、ろくろを使って頭と胴の部分をそれぞれ削り出します。
削り出した頭と胴の部分は、摩擦の力を利用し取り付けます。首入れと呼ばれ、首が回る特徴を持つ鳴子のこけしには特に重要な工程で、ここにもミズキの特徴が生かされています。
こけしの首部分は胴体の穴よりも大きいのですが、ミズキは柔らかく適度な弾力性があるため首入れが可能になるということです。
柿澤さんは他にも、木肌の白さなどといったミズキの特徴もこけし作りに生きていると言います。
柿澤こけし店柿澤是伸さん「白くて肌色っぽくて。こけしはお人形さんなので、ミズキは人形に適したような木肌だと思います。きめ細やかで木目が目立ちづらくて白っぽくて。建築材に使えないことによって、昔はミズキが多くあったのかもしれません、材料的にも。なので結構ミズキが使われることが多くなったと思いますけどね」
柿澤さんの工房では、伝統的なこけしだけではなくミズキの皮を生かした作品や季節の花を描いた小さなサイズの作品など、様々な種類のこけしを製作販売しています。
柿澤こけし店柿澤是伸さん「全部1本1本手描きで違う物なので、好みの物を見つけてもらうことが一番ですかね」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ