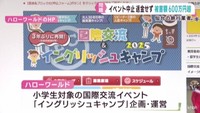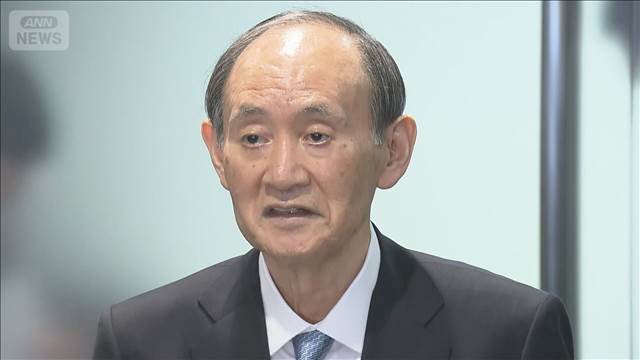米の価格高騰が続く中、稲作の現場では需要の増加に応えようと生産量アップを目指しています。米不足の解消につながるのか。その取り組みに迫ります。
日本人の食卓に欠かせない米の価格が高止まりし、前年の2倍以上の値段が続いています。こうした中、新たな栽培方法で生産量アップを目指す農家がいます。
農家「種の状態で水田にまいて育てるという育て方を、チャレンジしようと思っています。湛水直播栽培」
更に宮城県の試験場では、近年稲に深刻な被害をもたらしている猛暑に耐えられる品種の開発も。
研究員「ここ2年、大変暑い年が続いているのですが、その年でも品質が低下しないことが期待されています」
宮城県に12店舗を構える牛タン店には、平日の開店直後からたくさんの客でにぎわっています。人気の理由はご飯の大盛が無料で、更におかわりも1杯まで無料のサービスです。
「大盛でご飯頼んで食べました。それがあるからこの店に来ているという感じじゃないですかね」「ご飯が進む。おかわりしたいなって。お米高いからありがたいですね」
しかし、サービスを続ける店は頭を悩ませています。米の使用量は1カ月当たり全店舗合わせて約12トンで、仕入れ値が倍以上に膨らむ中、経営を圧迫しています。
たんや善治郎別館大山文郁店長「米は仕入れ値でも大きな割合を占めるので、厳しい現状は厳しい現状だと思います。サービスはやめたくないと思っているので、今後、価格改定するのかどうなのかというところは考えなくてはいけないと思いますけど、今は、現状維持のまま頑張っています」
全国のスーパーでの米の平均価格は、直近の1週間で5キロ当たり4268円です。前の週は2025年に入って初めて値下がりしていましたがそこから54円値上がりし、再び最高値を更新しました。
価格の高騰はいつまで続くのか。米の流通や価格の変動に詳しい宮城大学の大泉一貫名誉教授に聞きました。
宮城大学大泉一貫名誉教授「私は、米不足は相変わらず解消していないのだろうと思うんですよ。6月7月も、こういった水準で行くと思っているんですね。それで、危機的なのは端境期の8月末から9月の頃ですよね。その頃に果たして米が潤沢に出てくるかどうか。そういう情報が出てくるかどうかが1つの鍵だと思っています」
米不足解消の鍵となる今シーズンの新米について、田植えを迎えた農家は需要の増加に応えようと生産量アップに乗り出しています。
鈴木奏斗アナウンサー「こちらは元々大豆を育てていた畑だったんですが、米の収量を増やすために畑を田んぼに変えて稲の栽培に切り替えています」
大崎市古川の農家佐々木崇行さんは、大豆を育てる予定だった3ヘクタールで稲を育てることにしました。更に、高齢化で引退した農家の田んぼと大豆畑3.5ヘクタールを引き受け、ここも全て稲に当てることにしました。
佐々木崇行さん「一農家ではあるけれどもこの問題にはどうしても憂慮している部分があるので、米をもっと育てるというのが一番今の状況に対応する行動なのかなと思ったら、米は育てられるだけ育てたいなと思いますし」
宮城県やJAによりますと、2025年に宮城県で作付けする主食用米の作付面積は約6万ヘクタールと、国の方針を受けて前年より6パーセント増やす計画です。一方で作付面積の拡大には労力がかかります。そこで、佐々木さんは新しい栽培方法を取り入れました。
佐々木崇行さん「種の状態で水田にまいて育てるという育て方を、チャレンジしようと思っています。湛水直播栽培」
湛水直播とはどういった栽培方法なのか。佐々木さんはこれまで4月中旬からハウスで苗を育て、育った苗を田んぼに植えていました。湛水直播では、苗ではなく種の状態で直接田んぼにまいて育てます。
種まき用の機械の導入に約100万円がかかりましたが、苗作りや田植えの手間を省けるため作業時間を3割ほど削減できます。
佐々木崇行さん「一番って言っても過言ではないくらいの大変な作業が苗作り。苗箱の枚数も、何千枚とかになるんですね。これぐらいの規模になると田植えの作業だと人がどうしても必要になるんですね。苗運びが必要だったりとか。家族総出でやったりとかするけど、このやり方だと1人でもできる作業になるんですね。これからの規模拡大を見据えて、このシステムを導入した」
更に、近い将来を見据えた取り組みも進んでいます。米の品種改良をしている宮城県古川農業試験場が暑さに強い苗を新たに開発しました。
宮城県古川農業試験場増田秀平研究員「ここ2年大変暑い年が続いているのですが、その年でも品質が低下しないことが期待されています」
稲作ではここ数年猛暑による被害が深刻で、品質の低下と収穫量の減少につながり米不足の要因にもなりました。古川農業試験場では、農家からの要望を受け2018年から品種改良を開始し、2025年から本格的な試験栽培に乗り出しました。今後、病気のかかりやすさや収穫量などを確認し、5年後の普及を目指します。
宮城県古川農業試験場増田秀平研究員「生産者の方が作りやすいお米、消費者の方が食べておいしいと思うお米をできるだけ早く皆様のお手元に届けられるように試験を続けていきます」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ