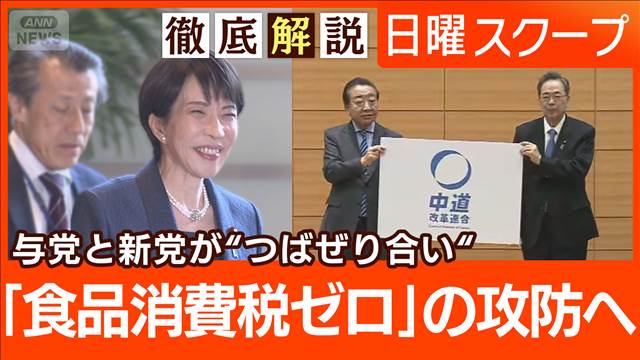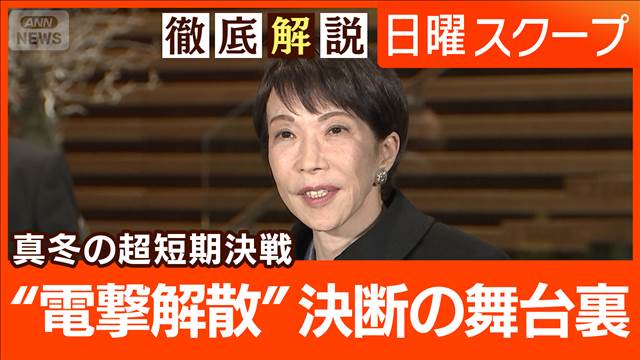災害時に子どもが弱い存在にならないように、事前に防災意識を高める取り組みです。大切なことは、経験を通して学ぶことです。
「地震の後、水道から水が出るようになったのでトイレをすぐに使っても良い」
仙台市太白区の八本松児童館で開催された防災キャンプは、小学2年生から6年生までの22人が避難所での生活を一晩体験します。
まずは、避難リュックを確認します。生活必需品のほかにも。
保護者「家族で写っている写真で、迎えに来た人が名前が分かったりするために使っています」
防災キャンプを企画した、児童館の松浦館長のおすすめは。
松浦大輔館長「結構明るいライトです。ペットボトルの水をこの上に乗せるとライトになります」
そして、子どもたちが何かを作っています。
「寝床やテーブルとか、段ボールで作ってました」「他の人とか混ざったりしちゃうから、壁を作って仕切っている」「仕切りでほこりを防いで、感染症とかの予防もできるように」
部屋を作り終えたらおやつの時間ですが、おやつといっても非常食のクラッカーとえいようかん。食べ慣れていないものを一度食べておくと、災害時のストレスの軽減になります。
午後9時に消灯。早速ペットボトルライトを実践するグループもみられました。
翌朝の午前4時半、起床時間の1時間半前ですが慣れない環境で目が覚めてしまった子どももいるようです。
避難所では生活時間が決まっている場合も多いため、起きてしまった子も起床時間までは静かに過ごします。
「夜から朝まで起きてたんだ」「寝袋が暑くて全然寝られなかった」「あまり眠れなかった」
防災キャンプを経験している子どはというと。
「前は1時間くらいしか寝られなかったから、良かったと思います。寝る時間になったら、ほとんどずっと寝ていました」「6時間寝られました」
災害時に何が起こるかを経験した子どもたち。学校防災に詳しい専門家も実体験をつくること、そして保護者との話し合いが大切だと話します。
東京大学小田隆史准教授「その経験が、実際の災害に直面した時に思い出してみて生きてくるということはあると思いますし、食べてみるものとかあるいは夜を過ごすために用意されている備蓄品への理解も深まるので、有効なことだと思います。都度都度の家庭での話し合いが非常に重要でして、その経験を踏まえた具体的な話し合いになっていくんでですね、こういった機会は重要で有効だと思います」
保護者「子どもに自分で考えさせることが大事なのかなって思ったので、なぜこれが必要なのかなとか、会話になった。いいきっかけになったので大人の分も見直してみようかなって思いました」「共同生活をするに当たってどうしても我慢しなければならない部分は、しっかり身に付けていってほしいと思うし、私自身も震災を経験してとても大事なことだと思います」
松浦大輔館長「災害が起こった時に親を助けてくれる、地域の皆さんも助けてくれる子どもたちに育ってほしいと願っております」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ