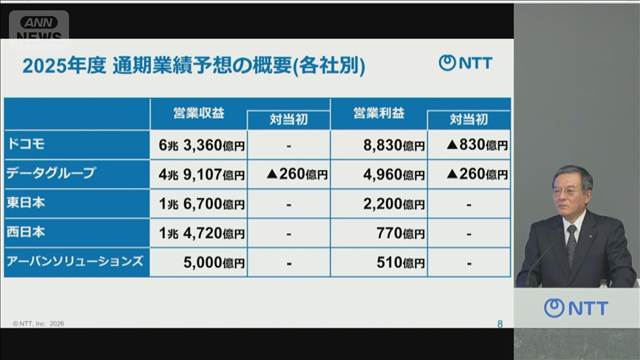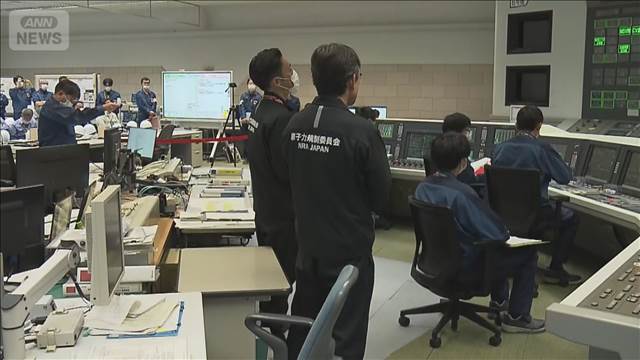水温が上がり変わりつつある三陸の海を、世代を超えて守るにはどうしたらいいか、行政と民間そして子どもたちが一緒に考えるプロジェクトがスタートしました。
プロジェクトの発足式が仙台市青葉区で行われ、宮城・福島・岩手3県の自治体職員らが出席しました。
近年、三陸沖の海水温は急上昇し、2023年以降平年より6土も高い状態が続いていて、取れる魚の種類が変わるなど影響が出ています。
プロジェクトでは、こうした問題を行政や水産業界で共有するにとどまらず、子どもたちにも伝えて海について考えていくことを目指します。
2025年度は全国展開するすしチェーンのスシローとコラボして、子どもたちが海産物を使ったオリジナルメニューを考案し、期間限定で販売する予定です。
こうした体験学習の様子を、映像コンテンツとして配信していきます。プロジェクトを監修するのは、東北大学理学研究科の杉本周作准教授です。
東北大学杉本周作准教授「子どもたちにとって一番なじみがあるのは魚だと思いますので、今三陸の海では何が取れるのか。そしてその前までは何が取れていたのか。その違いを理解することで変化を知り、そして今後について考える、そういうきっかけになればと思っています」
事業は日本財団が進める海と日本プロジェクトの一環に当たり、khb東日本放送が事務局を担います。

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ