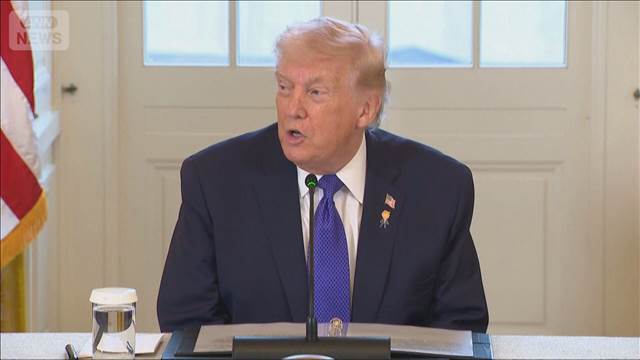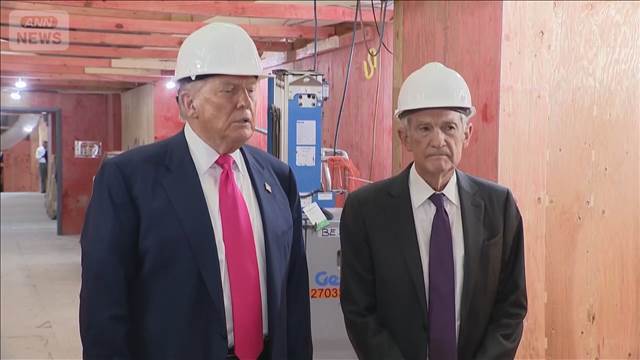産後ケアが近年広がりを見せています。1人でも多くのお母さんの声を拾いたいと、仙台市泉区の助産院が新たな取り組みを始めました。
泉区南光台にあるもちづき助産院は、出産後のお母さんが育児相談や休憩ができるようサポートする産後ケア専門の助産院です。院長の望月翔子さんは、9歳から0歳の4人の子どもを育てるお母さんです。泉区南光台で生まれ育ちました。
望月翔子さん「私自身南光台が大好きなので、地元に貢献したいというのが一番ですけど、子どもも増えている地区なので、南光台に住んでよかったと思ってもらえることを私もしたいと思って地元で開業しました」
助産院のスタッフは全員子育て真っ最中のお母さんです。少子化が進む中で、安心して子育てができるようにと仙台市では2018年から始まった産後ケア事業は、子育てに励むお母さんに休める場所を提供したり育児に関わる様々な相談に乗ったり、孤立しがちなお母さんを支える取り組みです。
仙台市では現在、67件の助産院などで産後ケアを実施していて、その利用者は年々増加しています。2024年度は1518組の親子が利用しました。
一方で、産後ケアを利用できるのは原則住民票がある自治体に限定され、利用できるのは1歳未満までと多くの制限があります。
望月翔子さん「産後ケアは1歳までしか使えなかったり、知らなかったと1回も助産院の門をたたかずに過ごされる方も多いので、少しでも助産院に足を運び入れるきっかけができたらと思い色々なイベントをやっている」
もちづき助産院の開院から2年、より多くのお母さんに助産院を知ってほしいと9月から赤ちゃん食堂を始めました。月齢に関係なくお母さんたちが集まれる場所として2022年に神奈川県で始まった取り組みで全国に52カ所、東北ではもちづき助産院が初めてです。
望月翔子さん「ずっと赤ちゃんと家にいて、どこかにお出掛けしたいなと思った時にお出掛けは1つのハードルかなと思っていて。ここに来れば何でもそろっているのが助産院のいいところだと思っている」
この日集まったのは、8カ月から1歳1カ月の子どもを育てる6人のお母さんです。ご飯までの時間は、保育士や子育て経験のあるボランティアスタッフと一緒に遊んだり、似たような悩みを持つお母さん同士で話したり話は尽きません。
お母さん「南光台出身なので助産院があることは知っていたが、京都に住んでいるので産後ケアは利用できなくて、こういう機会じゃないと来られないので」
この日はビビンバをメインに野菜中心のメニュー5品、6組の親子の食事を2人で作ります。
「離乳食だけでは作らずに、お母さんたちもこうやったら取り分けられるんだなと何となく分かるメニューにしています」
「赤ちゃんたちが持って食べやすいような大きさに切っています。小さいほうが危ないのでわざと大きく」
調理開始から1時間半。
「お野菜と鶏団子はスープと一緒に煮ていたものです。つかみながら食べて大丈夫です。あとはジャガイモとツナのボール、小松菜のおひたしです」
お母さん「すごく食べてるほう。みんな一緒に食べているので、私も食べようかなという気持ちに。この子おにぎりが好きだから、ジャガイモとかも丸くすれば食べてくれるかなっておうちでもやってみようと思いました」「他のお子さんを見て食べさせ方や、かじりとりができるようスティック状にしてもらっているので参考になる部分はたくさんある」「毎回同じような食材になったりとか作っても食べなかったりとか。すごく食いつきがいいです」
望月翔子さん「違う家庭の味を楽しめるのが助産院のいいところだと思うので、帰ってから助産院で作った物を作ってみようと思えるようなメニューになるように工夫しています」
子どもたちが食べ終えたらようやくお母さんのランチタイムです。食べやすいようにワンプレートに盛られた料理が運ばれてきました。食事中は助産院のスタッフが子どもたちの面倒を見ます。
お母さん「パンとかおにぎりとか丼物とか片手でさっと食べられるものになってしまうので、こうやって食事を用意してもらってゆっくり食べられると思うとうれしい」「人見知りがすごいので外に出かけても泣いてしまうことがすごく多いので、泣いてもいい場所があるのはありがたい」
参加したお母さんからは、温かいご飯を食べられる喜びや大人と話せてよかったという声も多く、その必要性を感じています。
望月翔子さん「自分の赤ちゃんが初めて赤ちゃんに触れる一番最初のスタートという方が多いので、ここに来れば寄り添ってもらえることがニーズになっている」
望月さんは、赤ちゃん食堂や助産院がお母さんと地域をつなぐ場所でありたいと話します。
望月翔子さん「困ったなという時に、一番最初に頭に浮かんでもらえる場所であったらいい。赤ちゃんじゃなくなっても遊びに行きたいと思ってもらえる場所」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ