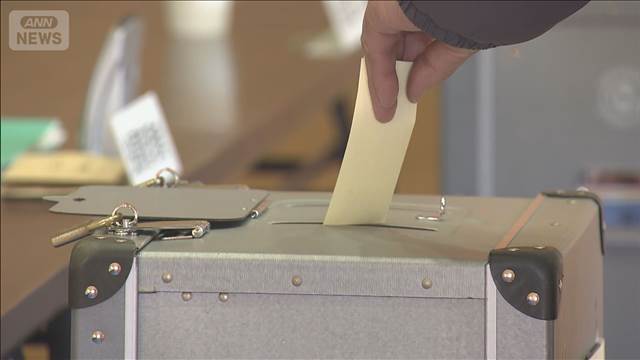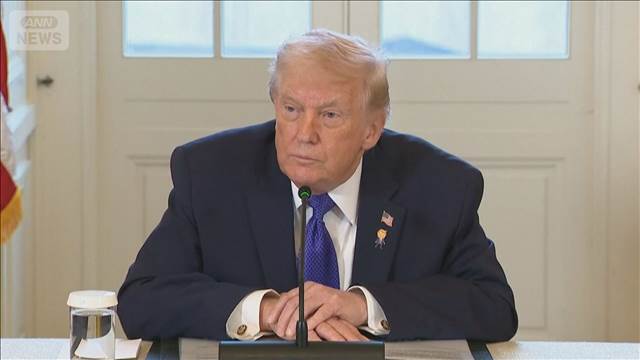需要の低迷に加え原料の米価格の高騰でピンチが続く日本酒、業界を変えようと宮城県の若手蔵元2人が異色の新商品を開発しました。
13日、宮城県で新たな日本酒の販売が始まりました。富谷市の内ヶ崎酒造店と白石市の蔵王酒造、2つの酒蔵がタッグを組みそれぞれの代表銘柄を1対1でブレンドしたケロハナ87です。原料である米を削る量が少ない低精白の製法ながら、削る量が多くなければ難しいとされる軽やかで飲みやすい口当たりを実現しました。
内ヶ崎酒造店内ヶ﨑啓社長「87%精米ということで非常に低精白なんですけれども、すっきりしてちょっとほんのりフルーティーになった。いいなと思って、そこにはすごいこだわりました」
蔵王酒造渡邊毅一郎社長「日本酒の概念を変えるとか現状を変えていこうという思いがあるので特に若い方、日本酒っておいしいんだなって日本酒っていいものなんだなという入り口として飲んでいたただきたいなと思っております」
気鋭の若手蔵元2人が仕掛けた挑戦の背景には、日本酒を取り巻く大変な逆風がありました。
朝晩の冷え込みが厳しさを増していた20日の白石市。この地で150年以上の歴史がある蔵王酒造です。朝早くから、甑(こしき)と呼ばれる大型のせいろが盛んに蒸気を上げていました。蒸されているのは日本酒の原料となる酒米です。
午前9時、酒造りが始まりました。この日行ったのは人気銘柄蔵王の仕込み作業で、使う酒米は約600キロです。
蒸し上がった米=蒸米をスコップで掘る作業には、社長の渡邊毅一郎さんもいち蔵人として加わります。
取り出した蒸米は機械で運ばれながら冷やされ、更にエアーシューターを伝ってタンクに投入されます。日本酒の前段階となる醪(もろみ)という液体です。蔵王酒造では、20日間から30日間かけて発酵させるということです。
翌日に蒸す米を洗う洗米の作業では、米に吸わせる水の量でお酒の品質が大きく変わるため感覚を研ぎ澄まして吸水量を見極めます。
渡邊毅一郎社長「片付けです。最後、一応これも全部入れちゃいます。基本は残さないようにしている。やっぱり基本的には無駄にならないように」
日本酒の原料の大部分は、米が占めています。それだけに昨今の価格高騰は酒蔵の経営に深刻な影響を与えています。
蔵王酒造渡邊毅一郎社長「お米の値段が上がる前と比べると、やっぱり倍ぐらいのイメージでお米の値段が上がっていますね」
JA全農みやぎは2025年、酒米を集荷する際に農家に前払いをする概算金について、蔵の華で1俵60キロ当たり2万8500円など軒並み引き上げました。
2024年からの値上がり幅は約1.7倍で、これに流通経費が乗ると酒蔵が支払う仕入れ値は約2倍もの大幅増になるケースもあると言われています。
蔵王酒造渡邊毅一郎社長「これをなかなか企業努力だけで賄えるかというと、やっぱりちょっと厳しいというところで、どうしても値段に転嫁しなければならないところが出てきたりとか。日本酒自体はやっぱり嗜好品なので、値段が上がるとどうしても飲む方が少し控えるという動きが出てきてしまうので。誰も幸せにならない値上げというか、自分たちも利益が増すわけではないので」
蔵王酒造でも年明けから値上げをせざるを得ないという渡邊さんが逆境を切り抜けようと、内ヶ崎酒造店の内ヶ﨑啓社長と開発したのが、新たな日本酒ケロハナ87です。特徴は、原料の酒米を有効に使うため精米の時に削る量を減らしたことです。
米を削って残す割合、精米歩合は87%と米の外側の13%しか削っていない計算です。国税庁の調査によると日本酒の平均の精米歩合は61.4%で、一般的には削る量が多いほど雑味が少なくすっきりとした味わいになるとされるなか、酒米の高騰を受けてあえて削らない製法に挑戦しました。
本来なら味が濃くて重たい酒に仕上がるところを、米の溶け具合を調整したり追加する水によって発酵をコントロールしたりすることで、狙い通りの味と量を両立させることに成功したということです。
蔵王酒造渡邊毅一郎社長「お米を少なく使いつつ、お酒はきちっと量を造るということです。やっぱり原価を抑えられるので、そこできちっとしたおいしいお酒ができれば、日本酒のスタンダードになっていく可能性っていうのはあるかなあと思います」
商品名の由来は精米歩合の87%に加え、渡邊さんと内ヶ﨑さんが共に1987年度生まれの同学年という共通点からです。2人の狙いは特にアルコール離れが進む若年層に日本酒の魅力を伝え、需要を掘り起こすこと。アルコール度数を平均より2%ほど低い13%と飲みやすくしたうえ、原価を抑えられた分、買い求めやすい価格に設定しました。
蔵王酒造渡邊毅一郎社長「おじさんの飲み物という意識がやっぱりまだまだ残っているかなと思うんですけれども、若い人間がどんどんお酒を造ってきたりだとかすごいフルーティーで軽やかな日本酒もどんどん出てきたりもしていますし、一度体験してみたりするとかなりイメージが変わるかなと思うんですけどね」
日本酒業界の現状を変える。日本酒の常識がひっくりかえる。モチーフのカエルにそんな願いも込めたケロハナ87の販売は、宮城県の酒屋のみです。自分たちがもうかるだけではなく、地元宮城県の日本酒造りを盛り上げたいという思いもあるということです。
蔵王酒造渡邊毅一郎社長「宮城県民の方って宮城県のお酒をすごい好きなんですよね、すごくありがたいことで、これが。まだまだ宮城県のお酒は面白いことをやっていくよ、おいしいお酒がまたどんどん出ていくよ、ということを知っていただきたいし、新しいファンの方をつくって、またこれから10年20年30年と宮城のお酒を愛していただいて、それをまたその方が外に広めていくっていう、その足掛かりというか1つの小さいものだと思うんですけど土台となってくれるならいいなあとは思っています」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ