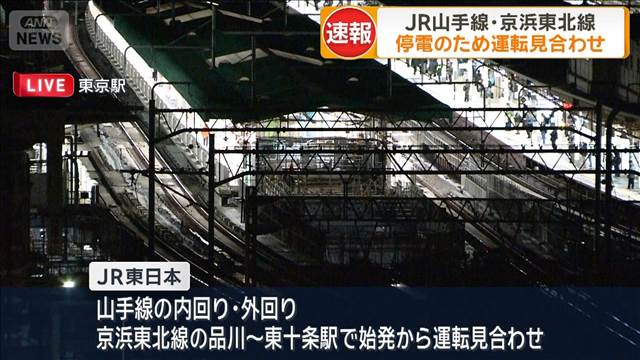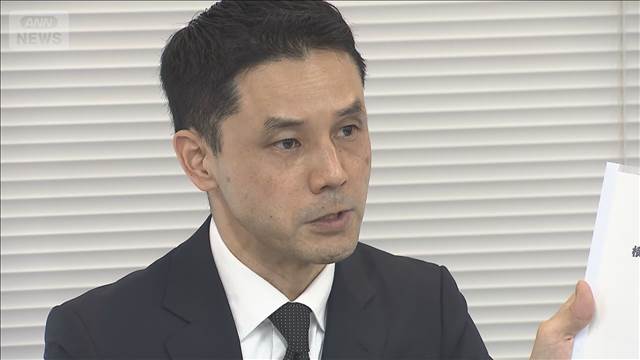不登校になった子どもたちなどを支援する、宮城県大崎市にある子どもの心のケアハウスの移転式が行われました。
子どもの心のケアハウスは、2019年に開設され老朽化のため移転することになりました。
不登校になった児童生徒やその保護者などをサポートする施設で、宮城県34の市町村が設置していて県が支援しています。
電話や面接による相談に福祉や心理の専門家が応じるほか、学習支援などを行っています。
大崎市の施設には2025年度、1カ月当たり20件ほどの相談があり、例年夏休み明けに相談が増える傾向があるということです。
佐々木誠道スーパーバイザー「丁寧に子どもたちから聞き取りを行ったり、保護者の話に寄り添って子どもたちが自立できるよう支援をして参りたいなと考えております」
新たな施設はJR古川駅近くに設置され、9月1日から利用が開始されます。
不登校に関する文部科学省の調査結果です。2023年度に宮城県の小中学校で30日以上欠席した不登校の児童生徒の数は7840人で、過去最多となっています。
小中学生1000人当たりの不登校数は宮城県は46.7人で、全国の都道府県で最も多くなりました。
不登校が増えやすいという夏休み明けに、背景や注意すべきポイントについて、仙台市で不登校児を受け入れている施設の担当者に話を聞きました。
青葉区水の森にある仙台市教育支援センターでは不登校の小中学生を約50人受け入れ、コミュニケーション活動や家庭への訪問など支援を行っています。
不登校の背景として担当者は、学校での勉強や人間関係、生活リズムの乱れなどでうまくいかないことがあった際に、気分が低下してしまい自己肯定感ややる気を失ってしまうことが大きいと言います。
仙台市教育支援センター遠藤晋所長「気持ちのエネルギーがどんどん低下していって、それでたどり着く子たちが多いんですね。一般的には、自己肯定感とか自尊感情と言いますね。そういう自己肯定感とか自己有用感が足りなくなってくると、大人もそうですけど色々なことにやる気が起きなってくるのかなと思いますね。子どもだとそれが登校に結びつかなかったりとか」
遠藤さんは不登校の背景にある低下した自己肯定感を高めるためには、まずは子どもの気持ちを受け止めること。そして例えば関心があることを見つけたり、周りが耳を傾けて気持ちを整理できるようにすることが大事と話します。
仙台市教育支援センター遠藤晋所長「あなたはそういうふうに考えているんだねって、子どものそういう気持ちに寄り添うことが大事だと思います」
子どもが抱える悩みは人ぞれぞれです。周りの方も対応に悩んだ場合は、専門家に相談することも大切です。
宮城県と仙台市では、登校の不安や悩みに関する相談を受け付けています。各自治体の子どもの心のケアハウスなどとも連携しています。

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ