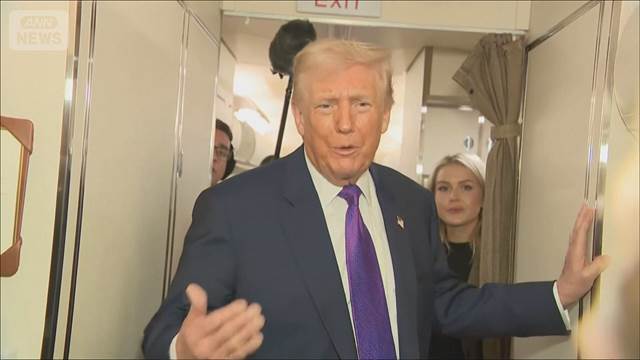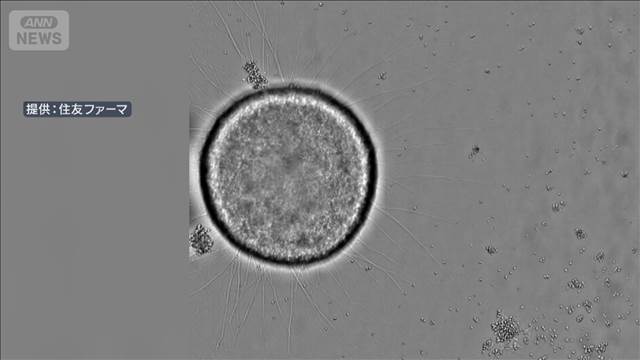東日本大震災で津波にのまれながらも九死に一生を得て、復興の陣頭指揮を執った南三陸町の佐藤仁前町長に震災の時の壮絶な体験や、その後の復興などを聞きました。
5日の退任式で佐藤さんは、震災当時を振り返りました。
佐藤仁南三陸町長「本当に痛恨の極みだった。多くの仲間を失いました。残念至極です」
そして、復興に力を尽くした職員へ感謝の言葉を述べました。
佐藤仁南三陸町長「ここにいる職員みんなの献身的な取り組みが、南三陸町の復興を成し遂げた大きな要因だと思っている」
退任から数日が経ち、佐藤さんがkhbの取材に応じ改めて震災当日の体験を語りました。
佐藤仁さん「ここが役場庁舎だった。これが役場庁舎でこの2階の向こうの川側が、議会だった。(議会に出席中に)震災になった。震災直後は気象庁の発表は(津波の高さが)6メートルということで、(防災防策庁舎の)屋上が12メートルでしたので、ここの2階から、ずっと防災対策庁舎の放送室から町民の避難誘導をずっと行っていた。目の前の川に津波が入ってきたので全員で屋上に避難しましたけど、みんな(津波の高さは)高さ6メートルという思いしかなかったので、屋上が12メートルなのでここまで来ないだろうと思いました」
しかし、想像さえしていなかった規模の津波が押し寄せました。
佐藤仁さん「最初に見たのはね、南三陸町は高さ5.5メートルの防潮堤をチリ地震津波の後に作りましたからそこを超えてきて、波が落ちたときに土煙がパッと黄色に上がったのを見たのが一番番最初で。その後は一気呵成で、住宅が全部流されて映画の特撮を見ているような状況でした」
Q.「水が来た時にはどのような感覚になりましたか」
佐藤仁さん「いやーそんなの見てる余裕なんかないですよ。一気に上がってくるっていうのは何かを考えるなんて余裕は全くないですから」
数十人が避難していた屋上で、津波が去った時に残っていたのは手すりにしがみついて助かった佐藤さんらわずか10人でした。更に10人はその夜、雪と強風により想像を絶する寒さに直面します。
佐藤仁さん「とにかく寒いを通り越している状況。全身ずぶぬれになりましたのでね、お互いにおしくらまんじゅうとかやったんですが。何の意味もないんですよ」
このままでは凍死すると思っていた時に、ある幸運に恵まれます。1人の職員のポケットに、ライターが入っていました。
佐藤仁さん「その職員がたばこを吸う職員だった。胸にたばことライターがありまして、そのライターが使えるんですよ。(元消防士の職員が)自分のネクタイを外して発泡スチロールとかベニヤ板とかを持ってきて細かく砕いて、それに火をつけてぼやっと煙が出た時にこれで何とか助かるかなと。もしその職員がたばこを吸わなかったら、間違いなく全員低体温で死んでいた」
その夜に職員と交わした言葉が、復興の原点となりました。
佐藤仁さん「生き残った我々がこの町を再建しなきゃいけないと。我々が頑張ってやらなければいけないなと。あそこで我々が再建を託されたという、それがずっと使命感として残ってきています。その思いだけでこの14年間ずっと走ってきた」
しかし、町は文字通り壊滅し多くの町民を失い途方に暮れます。
佐藤仁さん「まあ絶望的でしたね。もう見渡す限り全てが、がれきだらけでしたから。この町をどうやって再建するんだと、本当にできるのかとの思いの方が強かったですよね」
光が見えない中で、これだけはと決めたことがありました。
佐藤仁さん「この地域にはまた津波が来ると。2度と津波で(命を)失わない町をつくると。すべて住宅を高台移転するということを決めました」
南三陸町では全ての住宅が高台に建ち、自宅を津波で流される心配は無くなりました。復興の過程で課題となったのは、町の職員ら43人が亡くなった防災対策庁舎の保存です。建物を見たくないという遺族や町民も多く意見が割れましたが、佐藤さんは最終的に保存を決断しました。チリ地震津波で南三陸町が大きな被害を受けながら、それを伝える遺構が何も残っていなかったことへの悔いがありました。
佐藤仁さん「想定外のことが起きるんだよということを、将来の子どもたちにちゃんと伝えていく。そういう意味の役割としては、防災対策庁舎というのは大きい役割を担っていただいていると思う」
東日本大震災の発生から14年半が経ちました。災害の恐ろしさと復興の難しさを身を持って経験してきた佐藤さんは、行政には限界があることを知ってほしいと訴えます。
佐藤仁さん「市民町民が被災して、町の職員だけが被災しないということは無いんですよ。職員も同じように被災するんですよ。その職員が多くの市民町民を手助けすることはほぼ不可能。自分の命を誰も助けてくれませんので、自分が守るしかない。ということだけは、皆さんちゃんと胸にとどめておいていただければと私は思います」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ