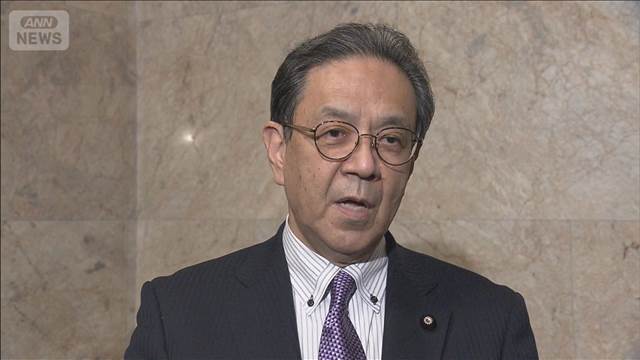東日本大震災の教訓を基に開発が進められてきたGPS付きライフジャケットの要となる、遭難した人を発見するシステムが完成しました。
GPS付きライフジャケットは、宮城県南三陸町が民間企業と連携して開発を進めています。
ライフジャケット自体は2024年に完成し、被災者を発見する位置情報システムの開発に移っていました。
そのシステムがこのほど完成し、2日に記者発表が行われました。
ガーディアン72有馬朱美社長「すごい大事に思ったのは1人1人、人数がしっかり把握できること。位置情報の中に他と紛れ込まないことで、数字が把握できる」
開発した東京都の企業ガーディアン72によりますと、今回は完全に新規のシステムを開発し既存の位置情報システムとは切り離した形で運用することで、ライフジャケットを身に着けている遭難者だけを確実に見つけられるということです。
救命救助隊とリアルタイムで情報を共有できますが、運用には自治体に受信局を設置してもらう必要があり、説明会などを開催して導入を働きかけていく考えです。
ガーディアン72有馬朱美社長「位置情報が分かるようになり、位置情報をどのように活用するか。公的な方々にどのように活用するかという事が、非常に大事になります」
将来的には、津波以外にも船の事故や河川の氾濫、土砂災害など遭難の可能性がある現場への導入を進めていきたいということです。
開発された3種類のGPS付きライフジャケットはスタンダードタイプ、既にライフジャケットを持っている人向けのGPS付きのフードタイプ、そして全身スーツタイプです。
GPS装置は電池式で、災害時に自動的にスイッチが入ります。72時間以上通信が可能で、50キロ以上離れた場所でも位置を把握できます。
これにより漁業関係者や救命関係者が乗る船だけではなく、海に近い地域の学校や高齢者施設での活用が期待されています。
GPS付きライフジャケットの開発の背景には、東日本大震災で同僚を失った宮城県南三陸町の職員の思いがありました。
GPS付きライフジャケットを提案した南三陸町職員の高橋一清さんは、東日本大震災の発生時に同僚ら43人が犠牲になった防災対策庁舎隣の役場庁舎にいましたが、避難所開設準備のため高台にある志津川中学校に向かいました。
その40分後、高台に移動した高橋さんは忘れることができない震災の津波を目撃します。
南三陸町職員高橋一清さん「防災対策庁舎の上で最後まで仲間たちが全力で頑張っていた姿を思い浮かべた時に、もしライフジャケットを着ていたらどう結果が変わったのかという思いがずっとありました」
こうして開発が始まったGPS付きライフジャケットは、東京都の企業ガーディアン72と連携して試行錯誤を繰り返し開発が進められました。
GPS装置は災害時に自動的にスイッチが入り72時間以上通信が可能で、50キロ以上離れた場所でも位置情報が把握できます。 これまでの実証実験では、沖合5キロにいるGPSの位置情報を町役場で取得し救助に向かうことなどを確認してきました。
低体温症やがれきとの衝突に備えるなど、震災の教訓をきっかけにあらゆるケースを想定し体全体を覆う全身スーツタイプも開発しました。
ガーディアン72有馬朱美社長「人の命を1人でも多く救うことに関して、可能性が広がってきたということを今感じています」
2日、海に流された被災者の位置情報を特定するGPSシステムが完成しました。
1人でも多くの命を救おうとする画期的な取り組みに、高橋さんは期待を寄せています。
南三陸町職員高橋一清さん「本格的にスタートして普及がどんどん進むことが次の災害に間に合うことにつながると思うので、そのスピード感が課題だと思ってますね」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ