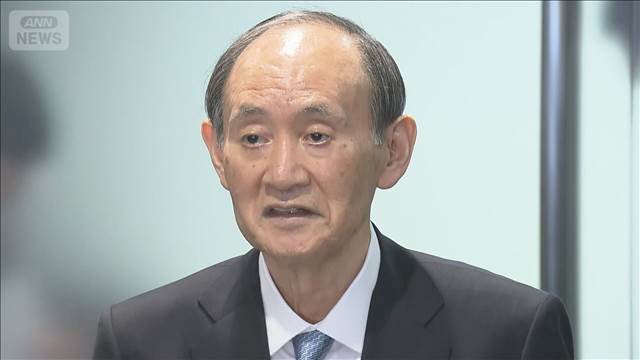17日から仙台の初夏の風物詩、仙台・青葉まつりが始まります。30年ぶりに新たな山鉾が加わるほか、初めて西公園をメイン会場に行われれます。会場では着々と準備が進んでいます。
青葉区の定禅寺通では、シンボルの伊達門が設置されるなど準備が進んでいます。41回目の今回は、すずめ踊りは前年より7団体多い134の祭連(まづら)が参加し、約4300人が華麗な演舞を披露します。
上野比呂企アナウンサー「大きい物では高さ6メートルほどにもなる山鉾。30年ぶりとなる新しい山鉾、アイリスオーヤマの山鉾が加わり12基が祭りを彩ります。祭りが終わった後に塗装を施すということで、白木の姿は今だけの貴重な姿となります。まだ木の香りがします」
市民「すごく楽しみです。お天気に恵まれるといいなって」「毎年楽しみにしているので、ここまで定着しているのはすごいなって思いますね」
青葉区一番町には、武将に扮した人や山鉾が街を巡る祭りのメインイベント時代絵巻巡行に参加する12基の山鉾が並んでいます。 上野比呂企アナウンサー「仙台市役所の建て替え工事で、西公園が勾当台公園市民広場に代わって初めてメイン会場となります。ステージや客席の設置作業が進められています。これまでの2倍以上の広さになったということです」
初めてメイン会場となった西公園では、踊りや太鼓などが披露される他、近くでは人力車の乗車体験もできるということです。
17日と18日の2日間で、約93万人の人出を見込んでいます。
仙台・青葉まつりの歴史を振り返ります。
現在のスタイルの仙台・青葉まつりは1985年(昭和60年)から始まりましたが、その前にも行われていました。
今から67年前の1958年(昭和33年)、仙台商工会議所などが主催して始まった初代の仙台青葉まつりでは、様々な飾り付けをした自動車などがパレードしています。中には、宇宙ステーションや、洋風の馬車もあります。
仙台・青葉まつり協賛会石黒大副実行委員長「古くは仙台祭という東照宮で開催されていたそうで、それはそれは大きいお祭りで、京都の祇園祭に引けを取らない」
仙台・青葉まつりのルーツは、江戸時代に始まった東照宮の仙台祭です。そして、青葉神社が創建された明治時代に始まった青葉まつり。この2つの例大祭を合わせて1956年(昭和31年)に始まったのが、初代の仙台青葉まつりです。
しかし、車の普及で交通量が増えたことから、1967年(昭和42年)を最後に、いったん終了してしまいます。
復活したのは、中断から18年後の1985年(昭和60年)です。現在のスタイルです。
伊達政宗の没後350年を記念して、見事に復活を遂げた仙台・青葉まつりでは、掛け声とともに神輿をかつぐ姿などが映っています。
1987年(昭和62年)には、大河ドラマの政宗ブームからすずめ踊りコンテストが始まりました。一度は消滅寸前だったすずめ踊りも、祭りに華を添える風物詩となりました。
1988年(昭和63年)から登場した山鉾は今回から12基に増え、仙台市民の祭りとして歴史をつないでいます。
仙台・青葉まつり協賛会石黒大副実行委員長「祭りがあるから頑張れる元気の源だったりきっかけだったり、市民にとっては無くてはならない。そういうような規模も大事ですけど、心のよりどころになるような祭りですよね」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ