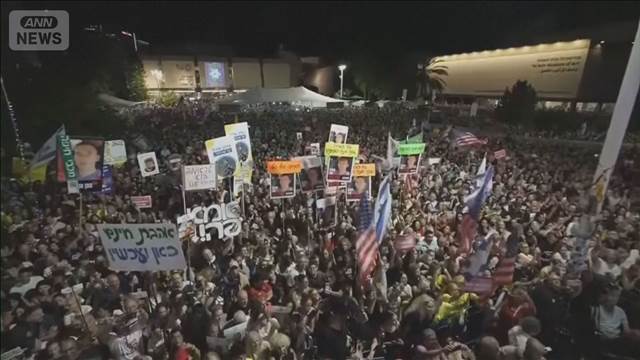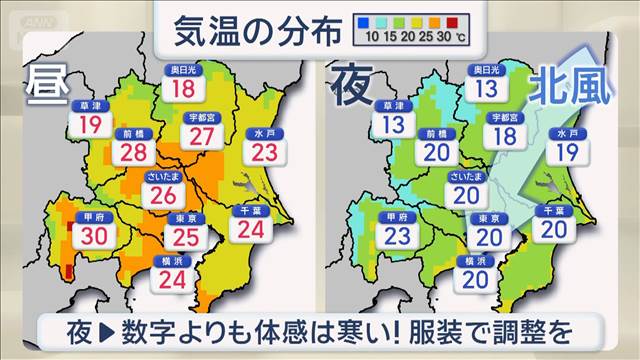自民党の高市早苗総裁と公明党の斉藤鉄夫代表は10月10日に会談し、連立政権の継続をめぐって協議を行ったが、意見の隔たりは埋まらず、両党の連立関係が決裂した。斉藤氏は会談後、記者団に対し「我々の要望に対して、自民党から明確かつ具体的な協力が得られなかった。改革が実現不可能なのであれば、とても首班指名で『高市早苗』と書くことはできない」と述べ、連立合意の「白紙」を宣言した。今回の会談において、公明党が要請したのは、企業・団体献金の規制強化、政治資金収支報告書の不記載問題の全容解明の2点。これに対し、自民党側は企業・団体献金の規制強化について、「基本的には、これから検討する」と述べるにとどめ、不記載問題についても「すでに決着済み」との立場を示したとされる。
斉藤氏はこれを受け、「(自民党は)『検討する』『検討する』。地方議員の声を聴かなければならないと1年前から言っている。何も行われない現実もある」と強い不満を表明した。さらに、不記載問題への姿勢についても「国民の感情とかけ離れており、これでは政治への信頼回復はおぼつかない」と批判。「自民党の不祥事を国民に説明し、応援することに地方議員を含め限界がきているのが現状だ」と語った。
これに対し、高市氏は党本部で記者団の取材に応じ、「私と幹事長と二人だけで政治資金規正法の細部に至るまで決めて帰ったら、まさに独裁でございます。それは、私はいたしません。党内の手続きをきちっと踏まなければ、他党と協議するにしても、責任のある自民党の姿勢は示せません」と述べ、拙速な合意形成を避け、適正手続きの必要性を示した。高市氏はさらに、「一方的に連立離脱を伝えられた」と主張。公明側の対応を明らかにした。これに対し、公明党の斉藤氏は「一方的に通告したわけではない。ずっと前から問題提起を重ねてきた」と反論。協議の過程をめぐっても、双方の主張は食い違った。
また、高市氏は「例えば総裁が私でなかったら、このような連立離脱ということはなかったのですかと伺いました。また、仮に総裁が代われば、再び連立協議を行う可能性はあるのかと尋ねました」と述べ、斉藤氏とのやり取りの一部を明らかにした。これに対し、公明党側は「今回の総裁選挙で誰が選ばれていても同じです」と説明したという。
自民と公明の関係悪化は、突然の決裂ではなく、ここ数年にわたり積み重なった不信感が背景にあると見られている。2023年9月、麻生太郎氏は、「公明党は(反撃能力の保有は)専守防衛に反するとして最後まで動かなかった。一番上の人たち、その裏にいる創価学会も含めて“動かなかったがん”だった」と述べ、公明党の幹部に異例の厳しい言葉を投げかけていた。
選挙区擁立をめぐり自公間に決定的な亀裂が生じる事案も発生していた。2023年、衆院小選挙区の「10増10減」によって新設された東京28区をめぐり、公明党は自前候補の擁立を目指した。だが、自民党側の賛同を得られず、最終的に断念に追い込まれた。当時の公明党幹事長だった石井啓一氏は、「東京における自公の信頼関係は地に落ちた」と強い言葉で批判した。当時、自民党東京都連会長を務めていたのが、萩生田光一氏だった。
★ゲスト:久江雅彦(共同通信特別編集委員)、林尚行(朝日新聞コンテンツ政策担当補佐役)、牧原出(東京大学先端科学技術研究センター教授) ★アンカー:末延吉正(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ