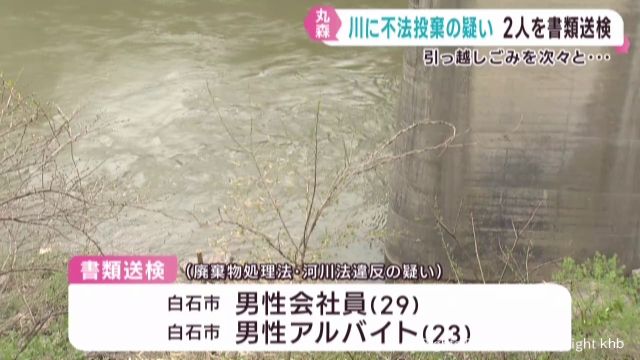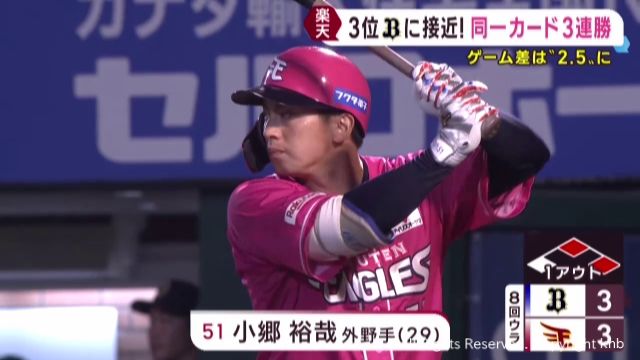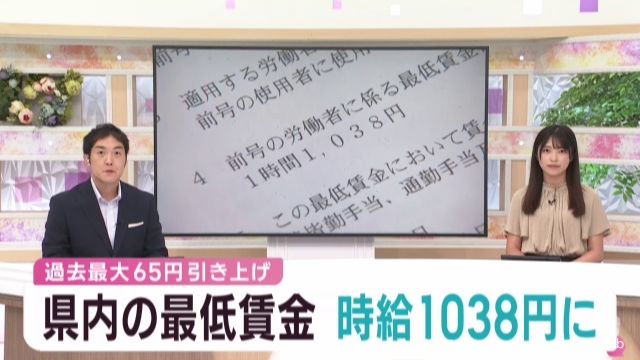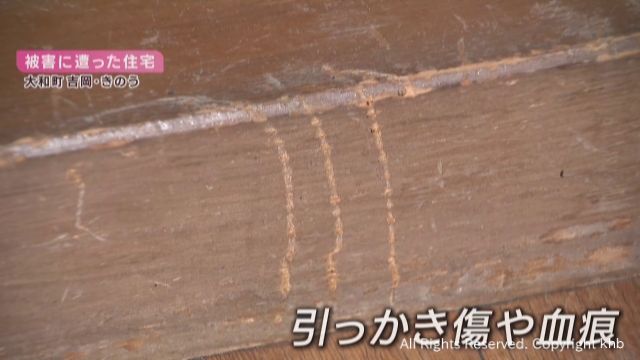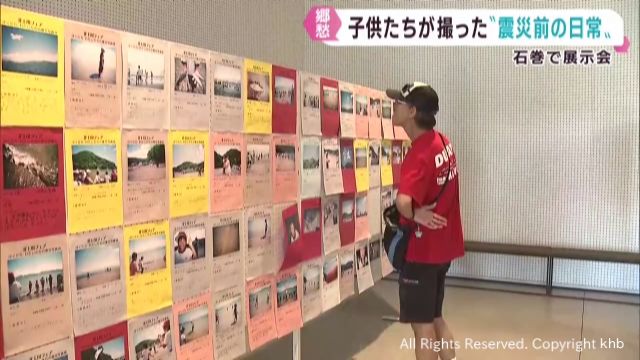研究者による引用回数が上位10%に入る「注目度の高い論文」の数で、日本は去年に続き過去最低の13位となりました。
文部科学省の「科学技術・学術政策研究所」は毎年、世界の主要な国の論文数などを調査しています。
その結果をもとに、2023年までの3年間に世界で発表された生物学や物理学などの論文を国ごとに分析した報告書が発表されました。
一般的に他の研究者による引用が多いほど内容が注目され質が高い論文とみなされ、研究成果のレべルを判断する一つの目安とされています。
報告書によりますと、他の論文に引用された回数が上位10%に入る「注目度の高い論文」の数で、日本は3447本で過去最低だった去年の発表と同じ13位でした。1位は中国で7万3315本でした。
また、上位1%に入る「トップ論文」の数でも中国が7458本で1位となりました。日本は293本で12位でした。
一方、「注目度の高い論文」がどこの国から引用されているかを調べた結果、中国の「注目度の高い論文」は自国内から引用されている割合が最も高いことが分かりました。
また、エジプトなどのグローバルサウス諸国は、自国または中国などから引用されている割合が高く、指標に影響している可能性も示唆されました。
科学技術・学術政策研究所は多様な観点から分析する必要があるとしたうえで、研究者の人材不足や研究時間の確保が十分でない環境などが順位にも影響していると分析しています。

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ