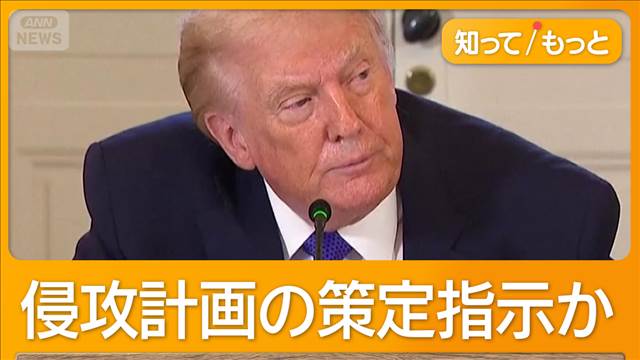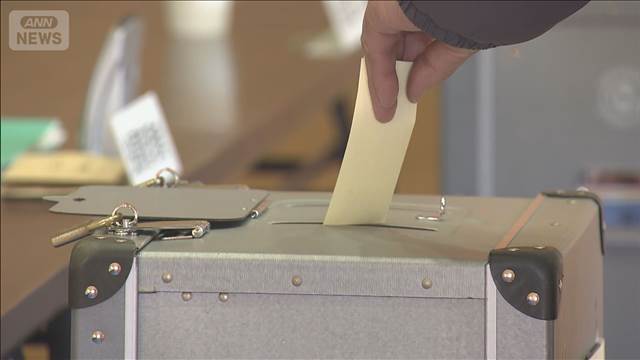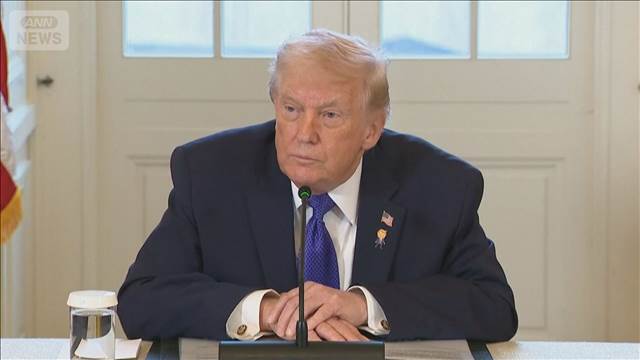拘禁刑の導入からまもなく半年です。刑罰のあり方が変わり、刑務所では新たな取り組みが進んでいます。一方で、罰が軽くなったのではと複雑な思いを抱く遺族もいます。
仙台市若林区にある宮城刑務所では6月の法改正で導入された新しい刑罰、拘禁刑に合わせて受刑者の処遇が大きく変わり始めています。
拘禁刑は、これまでの懲役刑と禁錮刑を一本化した制度です。
これまで懲役刑で義務だった刑務作業が義務ではなくなり、年齢や障害の有無など受刑者の特性に応じて個別に更生プログラムが組まれるようになりました。背景は、出所者の約3人に1人が再犯してしまう現実です。
この日行われていたのは、リフレクティングと呼ばれる新たな対話プログラムです。受刑者が自らの行動や気持ちを言語化し、自分を見つめ直すことを目的としています。
まずは受刑者と刑務官向き合い、じっくりと話を聞きます。他の刑務官2人は会話には加わらず、離れてその様子を見守ります。
受刑者「緊張しています。胸がドキドキしています。何しゃべっていいか分からないですね」
刑務官「今思っていること、話したいなと思っていることあれば」
受刑者の言葉を丁寧に引き出していく刑務官は、緊張している受刑者にリラックスしてもらうために時折笑顔を見せ、柔らかい口調で対話を続けます。
受刑者「今自分が感じていることは、全ての事に自分が感謝しなければいけない。言われたことに対して感謝。与えてもらっている食事に感謝。いかに感謝をするべきかというのは、今まだほんのささいですけど」
受刑者が話し終えると、今度は話を聞いていた2人の刑務官らが、第三者の立場から受け止めた印象を伝えます。
刑務官「回を重ねるごとに心の変化というものが出てきています」
職員「本人が一番気持ち良く良かったと思って刑務所の中ですけど、生活できているのは良かったと思います」
受刑者「言葉に表せば前進したってことですか。自分がね。微々たるものですが、少しでも自分が悔いを改められたということですね」
これまでは一方的に指導することが多かった刑務官は、受刑者との新たな向き合い方を模索しています。
刑務官「やはり話を聞くということですね。上から押さえつけない。まず話を聞いてみる。そこから何か改善策はあるんじゃないかって」
一方で、制度の変化を被害者や遺族はどのように受け止めているのでしょうか。交通事故で息子を亡くした佐々木尋貴さんは、事故をきっかけに事故調査の会社を立ち上げ、現在は様々な犯罪被害者の声を聞き続けています。
拘禁刑の導入について佐々木さんは、懲罰としての側面が薄れていくことに複雑な思いをがあります。
佐々木尋貴さん「まずやはり、懲罰という側面が失われていくことに納得できない部分はあると思います。懲罰から教育という方向にあまりにも極端にシフトしていくというのは、遺族として納得できない側面というのはある」
一方で、再犯防止のための仕組みそのものに反対しているわけではありません。
佐々木尋貴さん「遺族にとっては、やはり再犯っていうのはすごく辛いんですよね。再犯率が高いのは非常に辛いと思います。一体、自分の愛する人を大切な人の命が奪われて、そこから何も生まれなかったのかと」
再び罪を犯せば、亡くなった命からは何も生まれなかったことになってしまうからこそ、再犯を防ぐ仕組みづくりには期待もしています。
佐々木尋貴さん「やはり犯した罪に対しては懲罰の側面としてきちんと受けたうえで、再犯を下げるための制度は制度として生かしていくべきものだと思っているんですよ」
拘禁刑が導入されて何がどのように変わったのか、その変化をどのようにけ止めればいいのか、刑事政策に詳しい慶應義塾大学法学部の太田達也教授に聞きました。
拘禁刑制度の位置づけについて 「拘禁刑は受刑者の問題性を改善したり、強みを生かすための特性や課題に応じた処遇に十分な時間と体制を整える基盤ができた」と評価しています。
拘禁刑は、刑務作業中心の刑罰から再犯を減らすための処遇に比重を移したということになります。一方で、処遇が手厚くなる、刑が軽くなるのではという受け止めがあることも事実です。
太田教授は、被害者遺族が犯罪者の厳罰を求める気持ちは当然だとした上で、近年の制度改正で、被害者の視点を取り入れる動きが進んでいると話します。
慶應義塾大学法学部太田達也教授「拘禁刑に併せて、被害者の心情を聴取して刑務所の処遇に生かしたり受刑者に伝える制度や、仮釈放された後の保護観察でも加害者に向けた損害回復などの指導を強化する改正がなされていて、これまで受刑者の再犯防止が中心であった司法制度に被害者の視点が取り入れられています」
ただし拘禁刑を含めて、被害者支援にはまだ課題も残されています。その1つが、被害者への賠償をどのように実現していくのかという点です。受刑者が服役中に賠償へ踏み出す仕組みは、まだ十分ではありません。
慶應義塾大学法学部太田達也教授「改善更生とは、再犯を犯さないだけでなく被害者が被った被害に対しきちんと償いをしていくことが含まれて当然です。刑務所の時から、受刑者がわずかずつでも被害者に賠償をしていくための制度を作ることが絶対に必要です」
拘禁刑は、再犯を減らし被害者をこれ以上生まないための仕組みです。被害者の思いと加害者の改善の両方に向き合いながら、社会全体で再犯を減らすための議論を続けていくことが求められています。

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ