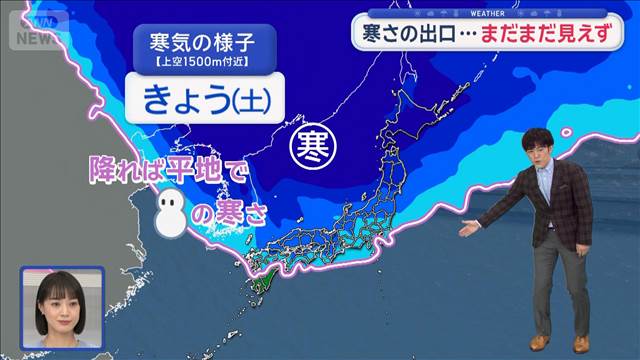8月に政府はこれまでの政策を転換し、米の増産にかじを切ると発表しました。宮城県の農家は増産は簡単ではないとした上で、政府は農家の経営が安定する政策を取ってほしいと訴えます。
小泉農水大臣「少しの需給の変動によって世の中に大きな混乱が生まれてしまうようなことがないような、政策体系へと転換をしなければいけない。それがまさに増産の方向性、この方向性にかじを切ると」
米不足に対応しようと、小泉農林水産大臣が歴史的な方針転換を示しました。
宮城県栗原市で農業生産法人を経営する白鳥正文さんは、88ヘクタールもの広大な農地でひとめぼれやつや姫など8品種の米を生産しています。
政府が強力に減反を推し進めていた時代も知る白鳥さんは、米の増産について農家として不安な面があると話します。
白鳥正文さん「必要な数量については生産していかなくちゃいけないということで、それはそれでいいんですけど、また米余りが起きて価格が暴落するというようなことも心配されますので」
増産をと言われても、難しい農家もいると話します。
白鳥正文さん「耕作放棄地となった田んぼをまた普通の田んぼに戻すっていうのは、それなりに経費とか重労働な部分は当然あると思います」
例えば、山間地などにある耕作放棄地は小さいサイズが多く、大きな農業機械は入らないということです。
白鳥さんは日本の米農家を守っていくためには、まず効率化が必要と訴えます。
白鳥正文さん「これからは大きい田んぼの作業性の高いほ場で、大型機械で効率の良い稲作をしていくことが主流だと思いますので、土地改良とかが必要になってきますね」
更に、米作りを安定させるためには価格の保障が大切で、それが無ければ米農家はいなくなってしまうと話します。
白鳥正文さん「米が高騰しているので、と価格を下げる政策をしてはだめだと思います。生産者がいなくなれば国民の方が飢えることになるので、生産者をきちんと維持できることが大切なんですよ」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ