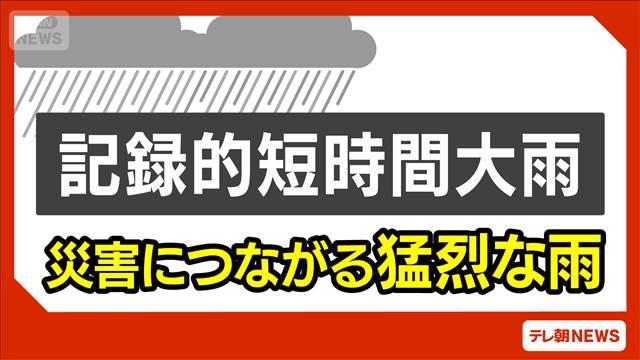琵琶湖にびっしりと生えているのは危険な外来植物です。驚異的な繁殖力で新米も脅かす侵略生物の駆除作戦を取材しました。
■琵琶湖ピンチ“侵略生物”大繁殖
2025年9月12日は作戦決行の日。ある場所に総勢200人ほどの若者が集結しました。
掛け声も飛び交う現場。一体、どういった作戦なのか。その作戦は貴重な新米をも脅かす“危険な侵略者”と関係していました。
コメ農家 毛利道郎さん 「キンバイ、キンバイと呼んでいる。厄介者です。コンバインで詰まる、(コメが)収穫できない、栄養も取られる、コメが悪くなる」
新米の収穫量を減らす恐れもある「キンバイ」。実は今回の作戦の目的は、そのキンバイを撃退することでした。一般的な雑草より根が深く、抜くのにも力がいる植物が侵略者の正体です。
京都大学大学院 地球環境学堂 田中周平准教授 「オオバナミズキンバイと言いまして、生態系を大きく改変させる恐れのある植物」
かれんな姿にだまされてはいけません。「オオバナミズキンバイ」は生態系などに被害を及ぼす「特定外来生物」。何といっても、その驚異的な繁殖力が特徴です。
千葉県柏市の川の水辺や京都府の鴨川でも。
今回、オオバナミズキンバイ撃退作戦が行われたのは日本一大きな湖「琵琶湖」のほとりです。
参加者 「1カ月前に見た時よりもどんどん大きく増えていて、上にも増えているし、迫ってきている。繁殖力に驚かされる」
琵琶湖では2009年ごろから急速に勢力を拡大。水面が覆われるばかりでなく、水中にも広がり、水質の悪化や固有の生態系への悪影響が懸念されています。
実はこの琵琶湖での状況がコメへの被害拡大についても鍵を握っていました。
京都大学大学院 地球環境学堂 田中周平准教授 「琵琶湖で一番生えている『ヨシ』はイネ科の植物。オオバナミズキンバイは『ヨシ』が生えているところで大きく広がっていったという特徴があるので、水田でも広がることは予想できた」
田んぼでは、琵琶湖以上に繁殖する恐れも…。
京都大学大学院 地球環境学堂 田中周平准教授 「(琵琶湖よりも)波が弱い水田で繁茂、稲と成育場所を奪い合う。栄養の供給も含めて影響を及ぼすことが考えられる」
刈り取っても茎から再度増殖するほど繁殖力が高いため、くまなく除去することが必要だということです。

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ