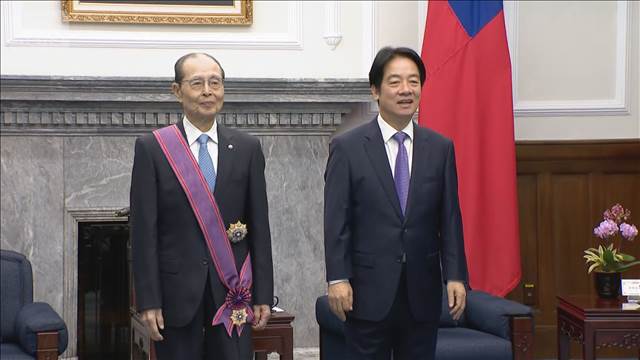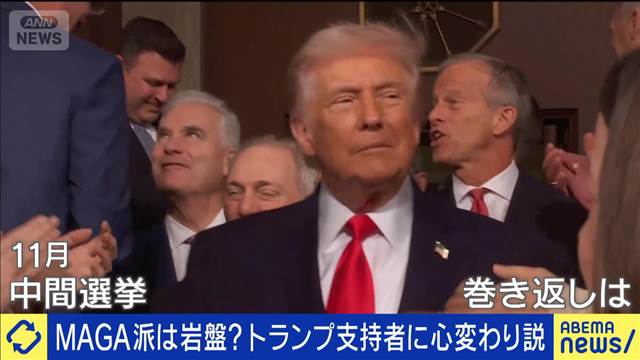2011年3月11日、巨大地震が宮城県を襲いました。死者は1万5900人に上ります。そのうち障害者の死亡率は全体の約2倍と言われています。誰のことも取り残さず“みんなで助かる”ために、今できることとは。防災特集「ソナエル」今回のテーマはあらゆる人の命を救おうという“インクルーシブ防災”。
東日本大震災では障害のある方の死亡率が高くなりました。大災害が発生した時、自分の命だけでなく、“全員で助かるために”今できることを考えます。
石巻市に住む及川幸男さん(69)は、38年前の仕事中の事故で車椅子生活となりました。食事や移動などはできますが、一人では難しい部分は妻の豊子さん(71)に手伝ってもらいながら暮らしています。
及川幸男さん「車椅子だから何としても人の手を借りなくちゃいけない。浴槽の介助、お風呂の介助、そういうのは全部妻頼みですね」
東日本大震災の日、及川さんは商業施設の中で大きな揺れを感じました。
及川幸男さん「ちょっと揺れてたでしょ。車椅子もボンボン飛ばされるんですよ、あの揺れで。荷物良く置いてあるテーブルありますでしょ、あそこにもうしがみついて、飛ばされないように」
その後、すぐに近くの中学校に避難し津波から逃れた及川さん。しかし、もし自宅に一人でいたら。
及川幸男さん「2階に上がるのにはね、階段昇降機ってつけてたんですけれども、電気が止まっちゃうでしょ、それ自体が動かくなるでしょ、終わりなんだろうなって」
震災での死者数は1万5900人に上ります。そのうち障害者の死亡率は住民全体の”2倍”と言われています。避難に手助けが必要な方が逃げ遅れてしまったのです。障害者福祉に詳しい専門家は、障害者避難に対する理解が足りなかったと指摘します。
東北福祉大学阿部利江講師「障害のある方々が地域でどんな生活をしていたのかを知らなかった人たちが多かったのかなっていうふうに思いますし、その方々に対する防災対策っていうところまで考えていなかった」
障害者や高齢者など弱い立場にある人も誰のことも取り残さないという防災の考え方を”インクルーシブ防災”と言います。どんなことに困りどんな助けが必要なのか。近くにいる人が知っておくことが大切です。
石巻市に住む芳賀和美さん(52)。ぶどう膜炎と緑内障の併発により左目はほとんど見えず、右目の視力も0.01ほど。震災当時右目の視力は矯正をすれば事務職の仕事ができるほどでしたが、震災時の極度のストレスなどにより症状は急激に悪化。あの日、門脇小学校近くの職場にいた芳賀さんは。
芳賀和美さん「壁のような黒いものが津波が押し寄せてきていて、崖の上まで逃げようとするんですけど、高さがちょっと足りなかったので、木の根っこだったり草の根っこだったり掴みながら、なんとか上りきった時には助かったって思って」
大災害の混乱の中では差し伸べられる手だけが頼りです。
芳賀和美さん「背中をこうやって触って押してもらうと怖いんですね。目をつぶって押されると怖いと思うんですけど、その状態になってしまうので失礼ながら肩とか腕とかひじのあたりを捕まらせてもらって、私の半歩前くらいを歩いてもらうとついていく形になるので、引っ張ってもらっている状態になるので、とても歩きやすいんです。お声がけは、お手伝いしましょうか?って声をかけていただけるのは一番ありがたいですね。大丈夫ですか?って言われるととっさに大丈夫ですって言ってしまう感じなので」
災害に備え今できることは人を知り、人とつながること。”みんなで助かる”ための第一歩は。
東北福祉大学阿部利江講師「日頃の中から障害のある方々から学ばなければいけないこともたくさんあると思っています。教科書であるような一般的な障害の特性を知るよりは身近に住んでいる方々を知っていくことが、まずは最初の一歩じゃないかなというふうに思います」
障害と一括りに言っても障害の内容や不自由なことも人それぞれ。その人に合った支援が必要そうです。さらに、無事に避難した後のことも考える必要があります。日常生活の支援が必要な方のために災害時に必要に応じて開設される”二次的な避難所”として「福祉避難所」があります。
福祉避難所は介護サービスや医療ケアなどの体制が整えられ、一般の指定避難所での生活が困難と判断された人が必要な支援を受けられる場所です。震災時も開設されましたが、介護者やボランティアなど「人手不足」が課題となりました。ただ、支援の内容によっては誰もが「人手」になり得ます。
東北福祉大学阿部利江講師「専門職でないとできない支援・援助っていうのは当然ありますので、そこは専門職に任せるっていうことが必要なんですが、それ以外でできることも実はたくさんあって、ボランティアっていう感覚で支援・援助をしていくっていうことで、お互いさまっていうことができたら良いのかなと思います。診察や治療などの支援のほかに、食事や移動のお手伝いなどを必要とされる方もいます。私たちも無理なくサポートできることからやっていけたらと思います」

 検索
検索
 お問い合わせ
お問い合わせ